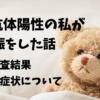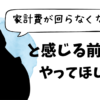吹奏楽部やオーケストラで使われる打楽器の種類と名前を詳しく紹介(画像付き)
打楽器(パーカッション)には全世界に多くの種類があります。その種類を画像、動画付きでご紹介いたします。
オーケストラの演奏や吹奏楽の演奏をコンサートなど鑑賞をした際、後ろで頑張っている楽器たち。それが、打楽器と言われるパートです。パーカッションとも言われています。
ただ演奏を聴くだけでは勿体無い!その楽器の名前を知っているだけでも、これから何処かで鑑賞する機会があった時に見方が変わるかもしれません。今回は、打楽器について調べてみました。よろしくお願いします。
打楽器とは
簡単に説明すると、口で演奏する楽器や弦楽器以外の楽器をまとめて打楽器と言います。演奏には手やバチ(木の棒)などを使用します。よくアフリカ民族の方が演奏している楽器をテレビなどで見ますが、それが打楽器です。
オーケストラでよく使用する打楽器の種類を紹介
オーケストラとは、主に弦楽器で構成された楽団の事を言います。吹奏楽に比べると、登場する回数が少ない印象です。
ティンパニ

4つの大きな太鼓からなる楽器です。見たことがある人も多いのではないでしょうか?一つ一つの太鼓は下のペダルを踏むことによって、音程を変えることができます。この音程は、演奏前に必ず演奏者が太鼓の端についている蛇口のようなチューニングボルトを回して、チューニング(音を調節する作業)を行なっており、毎回音程のズレがないようにしています。何故なら、演奏する場所の湿度や温度、移動時の振動などで音程が変わるからです。

チューニング時にチューニングボルトを回しますが、回す順番も決まっていたりします。一つの太鼓に6個から8個ほど付いていますが、対角線上にボルトを締めていきます。
他の太鼓と違い、正確な音程を出すことができるため、オーケストラでは『第二の指揮者』と呼ばれているようです。
ティンパニのおすすめ楽曲
ブラームス 交響曲
スネアドラム

小太鼓と言うと分かりやすいでしょうか?鼓笛隊などでもよく見かける太鼓です。スティックと呼ばれる木の棒で叩きますが、スティックの先が箒のようになっているブラシで擦って音を出す事もあります。この奏法はよくジャズで使用しているため、若しかしたらオーケストラでは一般的ではないかもしれません。

スネアドラムのおすすめ楽曲
ラヴェル ボレロ
バスドラム
一般的には大太鼓と言った方が分かりやすいかもしれません。スネアドラムと違ってスティックの先は、ボールのような形状になっています。


演奏中はなかなか目立たない楽器ではありますが、曲中で緊迫さを表現する時やティンパニと合わせて、オーケストラのリズムを刻んでいたりします。
叩く場所や使用するマレットによって音の質が変わります。また、ティンパニと同様にその場所の環境などによって、本革を張っているバスドラムの場合、音質が変わってしまう為、チューニングが必要です。
簡単なようで実が奥が深い楽器です。
バスドラムのおすすめ楽曲
J.シュトラウス2世 雷鳴と雷光
シンバル

金属の丸い鍋ブタのようなものを2つ使用するシンバル。
単純に2つを縦に合わせることで綺麗な音は出ない、意外と難しい楽器だと思います。
左へ15度くらい傾けて、右に持ったシンバルを左のシンバルへ擦り合わせる様なイメージで打ちます。

シンバルは金属なので、重さが2kgほどあり腕に負担がかかります。演奏者の腕はかなり鍛えられてようですね。また、汗などの水分でサビになりやすいので、乾いた布などでこまめに拭きます。
吹奏楽でよく使用する打楽器の種類
ここからは、吹奏楽でよく登場する打楽器です。
知人が学生時に吹奏楽部で打楽器を担当していたので、ここからは知人から聞いた吹奏楽部で使用する打楽器を紹介します。
※途中、楽器の使用方法や手入れ方法を入れますが、知人の経験を基に書いていますので、あくまで参考として下さい。
シロフォン
俗に言う木琴です。

木の板をピアノの鍵盤のように2列で並べられていますが、叩くと比較的硬い音がします。また、演奏に使用するバチをマレットと言いますが、マレットの先の硬さが柔らかいものや硬いものに変えることで音色に変化をつけることができる為、沢山のマレットを所有してます。演奏の曲調に合わせる為、自分でマレットの先をカスタマイズする人もいるようです。

打楽器の中でも、メロディーラインを担当することが多い楽器です。
また、楽器を演奏会などで別の会場へ移動する際には鍵盤部分を取り外して運びます。移動時に何かに接触して破損しないように、鍵盤部分は柔らかい布や毛布に包みます。
シロフォンのおすすめ楽曲
カバレフスキー 道化師のギャロップ
マリンバ

マリンバはシロフォンと同じ木琴の仲間です。
シロフォンよりも柔らかい音を奏でます。マレットはシロフォンと同じ形状ですが、シロフォンよりも鍵盤の木が柔らかい為、マレットの先も毛糸などで巻いたものを使用する事が多いです。

奏法はロールをしたり4本のマレットを使用して鍵盤を叩きます。マリンバは1人で演奏する他に、複数人で演奏する事もあり、打楽器の中でも1、2位を争う人気楽器だと思います。
マリンバのおすすめ楽曲
伊藤康英 ぐるぐるパーカッションより ぐるぐるマリンバ
グロッケンシュピール
こちらは、鉄琴の仲間です。

学校の教室にある、机ほどの大きさしかない小さな鍵盤楽器です。キラキラした音色が特徴で、曲中ではフルートと一緒にメロディーラインを担当したり、ソロも担当することがあります。
マレットは基本、シロフォンと同じものを使用しますが、先の球が小さく鉄の玉になっているマレットも曲調に合わせて使用します。

グロッケンはアタッシュケースのような黒い箱に入っていて、演奏時にはその下に三脚のような物を立てます。移動時はその箱を閉じてしまえば、傷つけずに運べます。
グロッケンシュピールのおすすめ楽曲
田嶋勉 エアーズ
ビブラフォン
こちらも、鉄琴の仲間です。グロッケンよりも柔らかい音色が特徴です。

ビブラフォンは電気を使用してパイプの内部と最上部についているファンを回し、ビブラートをかけて演奏することができます。マレットはビブラフォン専用のマレットやマリンバと同じマレットを使用したりします。

ビブラフォンのおすすめ楽曲
ルパン三世のテーマ‘80
タンバリン

小さいお子さんからお馴染みのタンバリン。吹奏楽では、クラシック曲だけではなくみんなが知っているJーPOPを演奏したりするので、タンバリンは大活躍します。
奏法はただ叩くだけではなく、手を卵を包むように少し丸めた状態で、手のひらではなく指先で叩きます。また、サムロールと言って親指や中指の腹をタンバリンの皮の部分に擦り付けて音を出す奏法もあります。
トライアングル
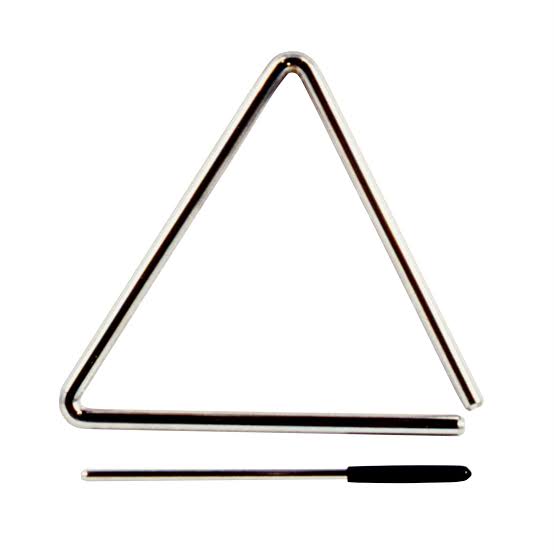
こちらの楽器もみなさんお馴染みのトライアングル。名の通り三角形の楽器です。叩くだけの楽器ではありますが、叩く場所によって音色が変わります。また、叩くときに使用する金属の棒をビーターと呼び、演奏者はその曲想に合わせてビーターの太さを変えたり、叩く場所やトライアングルの大きさを変えたりして、意外と奥深い楽器です。

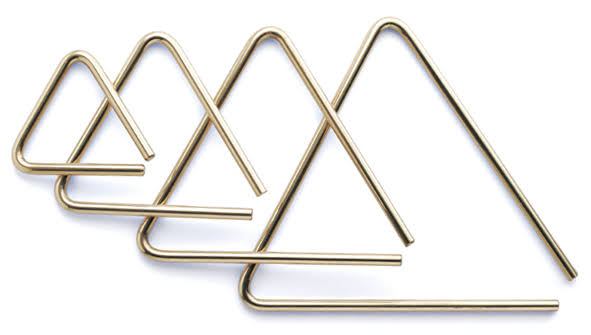
カスタネット
カスタネットは吹奏楽の打楽器でなくても、ご存知なのではないでしょうか。

よく幼稚園のお遊戯会や小学校の音楽の授業で使用した事があるという方が殆どだと思います。
吹奏楽で使用するカスタネットは、少し演奏方法が異なります。
皆さんが使っていたカスタネットは赤と青のカスタネットで、赤と青の木材を二枚貝のように重ねて紐で結んだ物を手で叩いていたかと思いますが、吹奏楽で使用するカスタネットは、二枚貝のような木材を紐で結びはしているものの、2つをつなげている程度で貝のような形にはなっていません。

さらに、このカスタネットを2セット使用して、自分の膝にぶつけて演奏したりします。頑張ってやりすぎると、膝にアザができてしまいます。
スレイベル
スレイベルは鈴なのですが、よく皆さんが想像するであろう鈴とは少し形が違います。
電車のつり革につかまるような感じで使用する鈴が1番ポピュラーな鈴です。これだと、音量が吹奏楽の演奏では小さい為、もっと沢山の鈴がついたものを使用します。それが、スレイベルです。
クリスマス曲を演奏する際には欠かせない打楽器の一つです。
そして、なにげに重いです。これを持って手首をひねるように音を鳴らしていると手首を負傷します。
マラカス

マラカスも、皆さんご存じの打楽器ですね。色々な種類のマラカスがあります。
プラスチック製のもの木製のもの。それぞれ音が違うようです。
曲に合ったマラカスを使用する為、沢山の種類のマラカスを所有する吹奏楽部もあるのではないでしょうか。
その他吹奏楽で使用する打楽器の種類
ここまで、みなさんがよく知っている打楽器達を紹介しました。ここからは、奏者なら知っているがあまり知られていない打楽器たちを紹介します。
ボンゴとコンガ
アフリカの音楽でよく登場しそうな楽器です。叩くときは手のひらを少し丸め、太鼓の縁を少し押し出すように叩きます。吹奏楽では、よく使用する楽器です。

カホン
箱型の打楽器で、叩く面が木製です。カホンの上に座って叩きます。裏には穴が空いておりそこから鈴や弦を仕込んで、音色を変化させる事もできます。

クラベス
2本の木の棒を打ち鳴らす楽器です。「火の用心!マッチ一本火事の元!!」でお馴染み“カンカン”といった音に似ています。

カウベル
名の通り、牛の首についてるベルのような楽器です。吹奏楽では、スネアドラムなどを叩くときに使用するバチを使ってベルの縁を叩きます。

アゴゴ
アゴゴはカウベルが2つついたような打楽器で、上下で音程が違います。一般的には交互に叩く楽器です。
通常は上下の2つだと思うのですが、中には3つ付いているアゴゴもあるようです。
アゴゴはサンバのリズムに欠かせない楽器です。

サンバホイッスル
サンバホイッスルはその名の通り、サンバを踊る時に使用する楽器です。笛なので、打楽器なのか?と問われたら最後ですが。吹奏楽では打楽器部員が担当する事が多いです。

何故ならば、管楽器担当の皆さんは口が空いていない(自分の楽器で口が塞がっている)からであり、打楽器担当は自分の楽器を叩きつつサンバホイッスルを吹ける、という事です。
スライドホイッスル

スライドホイッスルはサンバホイッスルと同じく、笛なのですが打楽器が担当する楽器です。形は縦長で下から突き刺さっている棒を下にゆっくり引き出すと同時に、上から笛のように息を入れる事で音程が変化します。
個人的はとても好きな打楽器です。
ウッドブロック
こちらも名の通り、箱型の木材をシロフォンなどで使用するマレットで叩きます。音色はお寺などでよく耳にする木魚に似ています。

チャイム
こちらは、NHKの日曜日お昼の番組でおなじみですね。調律されたパイプの上部をハンマーのようなバチで叩きます。パイプの長さは1mから2mあり、少し身長が低い人はパイプの上部に届かない。という問題が発生します。

ウィンドチャイム
この楽器は上記のチャイムよりも小型で、楽器を使用する時は自分の指かトライアングルを鳴らすときに使うスティックを使っています。
ウィンドチャイムの音は、星が流れる音を表すときに使われることが多いのではという印象です。
とても綺麗な音なので、よく吹奏楽の演奏ではソロを任されていたり、ウィンドチャイムの音から始まる曲を演奏することも多々あります。

フレクサトーン
こちらの楽器はなかなか所有している学校はないかと思います。実は、ガンダムのニュータイプの効果音として使用してます。また、2019年の吹奏楽コンクール課題曲Ⅴ「ビスマス・サイケデリアⅠ」でも使用するようです。

ギロ

ギロは擦り付ける楽器です。
イメージとしては昔、多くのお母さんが使用していただろう洗濯板を、箸で擦る時の音です。まあ、今実践することは少し難しいかもしれませんが。
ギロはとっても簡単な楽器なので、もしかしたら小学校の音楽室にもあったり、演奏したりしたことがある子もいるかもしれませんね。
ギロはいろんな形、色があります。なので、個性揃いの打楽器といえるのではないでしょうか。
オーケストラの楽曲では、物を動かす音を表現する時に登場します。代表的な楽曲は、ルロイ・アンダーソンの「タイプライター」でしょうか?
カバサ

カバサはとてもマニアックな楽器です。
この楽器を知っている方は相当な打楽器通かもしれません。
南米発祥の楽器であるカバサは、そもそもひょうたんの周りに溝を作って、そこに糸を通した数珠を擦り付けて音を出す楽器ですが、擦り付けるので想像されるような音がでます。
他の楽器で言うと、マラカスやギロの音に近いかもしれません。
ムチ
打楽器ではムチも楽器として使用します。
ですが、皆さんが想像するような、あの怖い鞭とは違います。演奏に使用するムチは木材を2枚蝶番で繋げたものを使用します。
ムチは楽器店で購入しなくても、自分たちで簡単に作成するが可能なので、出したい音を求める為に、色んな木材を使用してみたり長さを変えてみたり、工夫をしているところもあるようです。
スチールパン(スチールドラム)

スチールパンはトリニダード・ドバゴは発祥の打楽器です。
スチールパンはスチールドラムという名前で記憶している方がいますが、正しい名前はスチールパンです。
スチールドラムというのは、スチールパンを作る際に使用するドラム缶の名前です。なぜか、世間には材料名が楽器名として広まってしまいました。
スチールパンが誕生したのは第二次世界大戦後なので、他の楽器よりも歴史が浅い打楽器です。どんな楽器かというと、表面を部分部分叩いてヘコませて音程を作り出しています。イメージをしやすいのは、ドラム缶です。
音はドラム缶から出るとは想像のつかないような、とても不思議な音です。是非、皆さんにも聞いて欲しい打楽器のひとつです。
打楽器のおすすめ楽曲
たくさんの打楽器が登場する吹奏楽の楽曲です。
酒井 格 たなばた
打楽器の種類が学べる書籍を紹介
ここまでたくさんの打楽器を紹介しました。本当に打楽器って奥深いですね。ここからは、上記で紹介した打楽器を含めて色々な打楽器を紹介した書籍を紹介します。
打楽器アンサンブルコンテストについて
全日本吹奏楽連盟と朝日新聞社が主催して毎年3月に行われているコンテストです。
普段はたくさんの人数で演奏をしていますが、アンサンブルコンテストでは楽器別に3人から8人程度でコンテストに挑みます。打楽器は4重奏や6重奏、8重奏で多くのチームが出場します。
打楽器は他の楽器に比べるとたくさんの楽器の種類がある為、コンテストではありますが見ていて飽きません。
毎年12月ごろから地区予選が各地で行われているので、興味がある方は各地の吹奏楽連盟から検索してみてください。
以上です。ありがとうございました。